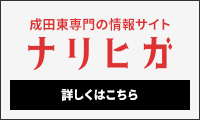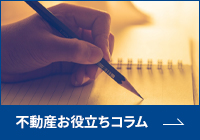贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) | 誠和不動産販売株式会社
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
著:金成 明洋 2024年12月更新
著:金成 明洋 2024年12月更新
1. はじめに
無償で財産が渡されることを「贈与」といいます。原則として、個人が受け取った1年間の贈与総額が110万円を超えた場合にかかってくるのが「贈与税」です。この贈与税は、たとえ親子や夫婦の間で行われた贈与であっても支払い義務が生じます。そのため、贈与を行う場合はその仕組みをしっかりと把握しておかないと、思わぬ税負担に驚くことがあります。
贈与の対象となる財産は現金以外にもあり、特に不動産を贈与する場合は注意が必要です。評価額が高いため、それだけ贈与税額も大きくなりがちだからです。ただし、不動産の贈与に関してはいくつかの特例が設けられており、それを使うことによって税負担を軽減することができます。例えば長年連れ添った夫婦であれば、贈与税ゼロで不動産を配偶者に譲れることもあるのです。
今回は、居住用不動産の非課税贈与特例である「贈与税の配偶者控除」について解説いたします。
2. 贈与税の配偶者控除の概要
一定の条件をクリアすれば、「贈与税の配偶者控除」という特例を受けることができます。
居住用不動産の贈与を受けた場合、基礎控除と合わせて2,110万円までの控除が受けられます。この制度は、夫婦間で居住財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、合わせて2,110万円までは非課税になるというものです。
3. 贈与税の配偶者控除を利用するための条件
この特例の適用を受けるには、以下の条件をクリアしていることが必要になります。
● 結婚して20年以上の夫婦であること
● 居住用不動産そのもの(または、居住用不動産を取得するための金銭であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
● 同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
● 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること
これらの条件をすべて満たしている場合、必要書類を添えて税務署長に贈与税の申告書を提出することによって、この特例の適用を受けることができます。
4. 贈与税の配偶者控除のメリット
この特例は、財産をもらったときに贈与税が軽減できるというだけではなく、贈与者の相続時などにもメリットがあります。
相続税を少なくすることができる
相続税は亡くなった人の財産に対して課税される税金ですが、その財産の一部を生前に配偶者へ移転することにより、課税遺産総額を減らすことができるため、結果的に相続税も少なくすることができます。
相続開始前3年以内の贈与財産の加算が適用されない
贈与者が亡くなるまでの3年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象になります。これは、余命が短いとわかってから急いで生前贈与をするなど、相続税を不当に少なくする行為を防ぐ目的があります。
※令和6年以降に贈与される財産は、相続税の課税対象になる期間が「亡くなるまでの7年以内」まで段階的に延長されます。
ただし、贈与税の配偶者控除で贈与された不動産や資金は、亡くなるまでの3年~7年以内の贈与であっても相続税の課税対象に加算しません。
自宅の売却時に夫婦2名で3,000万円特別控除が使える
将来自宅を売却する予定がある場合も、贈与税の配偶者控除が活用できます。この特例は、不動産の全てではなく、持分を決めて贈与することもできます。自宅の土地・家屋のうち2,000万円分の持分を、配偶者に贈与します。これにより自宅は夫婦の共有となります。将来この自宅を売却するときには、譲渡所得税の居住用財産の特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)を適用することができます。
この特例は、居住用財産を売却して利益を得た場合に、譲渡所得税の計算上3,000万円まで控除できるというものです。この3,000万円の特別控除は、物件ごとに適用するのではなく所有者ごとに適用することができます。つまり、夫婦で共有していた自宅を売却した場合は、売却益からそれぞれ3,000万円ずつ、合わせて6,000万円まで控除することができます。
5. 贈与税の配偶者控除利用の注意点
コスト面
相続する場合に比べて不動産の名義を変更する費用が高くなります。
不動産登記に必要な登録免許税は、相続の場合は固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与の場合では税率が2.0%になります。さらに、贈与では不動産取得税がかかります。不動産取得税については、相続の場合は非課税ですが、贈与の場合は固定資産税評価額の2分の1に対して3%の税金がかかります。
贈与を受けた配偶者が先に亡くなる場合も
贈与を受けた配偶者が先に亡くなることも考えておかなければなりません。
贈与を受けた配偶者が先に亡くなって、自分以外の相続人がいなければ、財産は自分のもとに戻ります。この場合は、費用と手間をかけて贈与をした意味がなくなってしまいます。一方、夫婦の間に子供がいない場合は、財産が配偶者の親族(両親または兄弟姉妹)のもとに渡る場合もあります。
6. 最後に
贈与税の配偶者控除を適用するには、贈与税の申告が必要です。
↑太線にした理由は、贈与税がかからないのであれば申告が必要ないと思われている方が多いためです。
申告をしないと、適用が認められないため、多額の贈与税を支払うことになります。
申告期日は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。ご注意ください。
無償で財産が渡されることを「贈与」といいます。原則として、個人が受け取った1年間の贈与総額が110万円を超えた場合にかかってくるのが「贈与税」です。この贈与税は、たとえ親子や夫婦の間で行われた贈与であっても支払い義務が生じます。そのため、贈与を行う場合はその仕組みをしっかりと把握しておかないと、思わぬ税負担に驚くことがあります。
贈与の対象となる財産は現金以外にもあり、特に不動産を贈与する場合は注意が必要です。評価額が高いため、それだけ贈与税額も大きくなりがちだからです。ただし、不動産の贈与に関してはいくつかの特例が設けられており、それを使うことによって税負担を軽減することができます。例えば長年連れ添った夫婦であれば、贈与税ゼロで不動産を配偶者に譲れることもあるのです。
今回は、居住用不動産の非課税贈与特例である「贈与税の配偶者控除」について解説いたします。
2. 贈与税の配偶者控除の概要
一定の条件をクリアすれば、「贈与税の配偶者控除」という特例を受けることができます。
居住用不動産の贈与を受けた場合、基礎控除と合わせて2,110万円までの控除が受けられます。この制度は、夫婦間で居住財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、合わせて2,110万円までは非課税になるというものです。
3. 贈与税の配偶者控除を利用するための条件
この特例の適用を受けるには、以下の条件をクリアしていることが必要になります。
● 結婚して20年以上の夫婦であること
● 居住用不動産そのもの(または、居住用不動産を取得するための金銭であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
● 同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
● 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること
これらの条件をすべて満たしている場合、必要書類を添えて税務署長に贈与税の申告書を提出することによって、この特例の適用を受けることができます。
4. 贈与税の配偶者控除のメリット
この特例は、財産をもらったときに贈与税が軽減できるというだけではなく、贈与者の相続時などにもメリットがあります。
相続税を少なくすることができる
相続税は亡くなった人の財産に対して課税される税金ですが、その財産の一部を生前に配偶者へ移転することにより、課税遺産総額を減らすことができるため、結果的に相続税も少なくすることができます。
相続開始前3年以内の贈与財産の加算が適用されない
贈与者が亡くなるまでの3年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象になります。これは、余命が短いとわかってから急いで生前贈与をするなど、相続税を不当に少なくする行為を防ぐ目的があります。
※令和6年以降に贈与される財産は、相続税の課税対象になる期間が「亡くなるまでの7年以内」まで段階的に延長されます。
ただし、贈与税の配偶者控除で贈与された不動産や資金は、亡くなるまでの3年~7年以内の贈与であっても相続税の課税対象に加算しません。
自宅の売却時に夫婦2名で3,000万円特別控除が使える
将来自宅を売却する予定がある場合も、贈与税の配偶者控除が活用できます。この特例は、不動産の全てではなく、持分を決めて贈与することもできます。自宅の土地・家屋のうち2,000万円分の持分を、配偶者に贈与します。これにより自宅は夫婦の共有となります。将来この自宅を売却するときには、譲渡所得税の居住用財産の特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)を適用することができます。
この特例は、居住用財産を売却して利益を得た場合に、譲渡所得税の計算上3,000万円まで控除できるというものです。この3,000万円の特別控除は、物件ごとに適用するのではなく所有者ごとに適用することができます。つまり、夫婦で共有していた自宅を売却した場合は、売却益からそれぞれ3,000万円ずつ、合わせて6,000万円まで控除することができます。
5. 贈与税の配偶者控除利用の注意点
コスト面
相続する場合に比べて不動産の名義を変更する費用が高くなります。
不動産登記に必要な登録免許税は、相続の場合は固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与の場合では税率が2.0%になります。さらに、贈与では不動産取得税がかかります。不動産取得税については、相続の場合は非課税ですが、贈与の場合は固定資産税評価額の2分の1に対して3%の税金がかかります。
贈与を受けた配偶者が先に亡くなる場合も
贈与を受けた配偶者が先に亡くなることも考えておかなければなりません。
贈与を受けた配偶者が先に亡くなって、自分以外の相続人がいなければ、財産は自分のもとに戻ります。この場合は、費用と手間をかけて贈与をした意味がなくなってしまいます。一方、夫婦の間に子供がいない場合は、財産が配偶者の親族(両親または兄弟姉妹)のもとに渡る場合もあります。
6. 最後に
贈与税の配偶者控除を適用するには、贈与税の申告が必要です。
↑太線にした理由は、贈与税がかからないのであれば申告が必要ないと思われている方が多いためです。
申告をしないと、適用が認められないため、多額の贈与税を支払うことになります。
申告期日は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。ご注意ください。

特集一覧
Copyright 杉並区阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷の不動産のことなら SEIWA-REAL-ESTATE All Rights reserved.